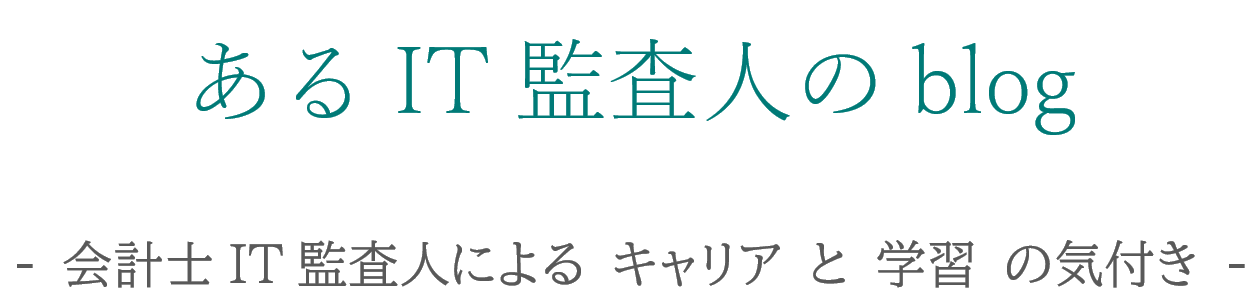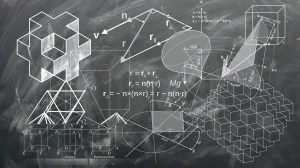世の中には、とてつもなく勉強ができる人、高い点数を取れる人というのが一定数います。そういう遺伝的に頭の回転や記憶力の優れた方がいるのは確かだと思います。
しかし、大多数の人はそうではありません。
もしあなたが、
「どうしても覚えられない、忘れてしまう」
「難しくてなかなか頭に入ってこない」
「勉強方法についてばかり悩み、なかなか要領よく、勉強が進まない」
という悩みを持っているなら、それは解決可能です。
なぜならば、それはおそらく、「勉強スキル」が足りていないか、あるいは、勉強の本質をいまいちよく理解していないから、だと思うからです。
断言しますが、テストで点数を取る力というのは、単なる「スキル」です。
そして、あとは「実行」するだけです。頭の良しあしは、会計士試験レベルではそこまで問題にはなりません。
人間の頭の構造はみな共通しています。その構造にしたがった勉強をすれば、自ずと誰でも結果を出せるようになります。それが「勉強スキル」です。
ということで今回は、前回からの続きで、私が受験時代に一番大事にしていた以下2つの事のうち、2つ目の「勉強スキル」についてです。
2.基本的な勉強スキルを体得する(今回の投稿)
前回の記事で、マインドや習慣といった部分に着目しました。
今回の記事では、テストで点数を取るためのスキル、勉強方法そのものにフォーカスします。
2014年度に公認会計士試験に合格したときの成績表と勉強法まとめは、こちらからどうぞ。

「勉強スキル」とは何か
テストで点数を取るための「勉強スキル」とは以下の3つを指します。
スキル②: インプットとアウトプットを相互に繰り返す
スキル③: 理解が難しい事も、分解すれば、一つ一つのパーツは理解可能な事である
それぞれを具体的に深掘りしていきます。
スキル①記憶して忘れて、また戻って記憶する、を繰り返す
忘れることを前提に勉強する
記憶についてはでは、エビングハウスの忘却曲線というものがよく知られていますよね。
(→人は1度勉強したことを1時間後に56%忘れ、1日後には74%、1週間後には77%、1カ月後には79%を忘れるいうデータあります。)
結論から言うと、このエビングハウスの忘却曲線に基づいて、学習スケジュールを立てる、なんてことはしなくOKです。
そんなガチガチにしばられた学習スタイルは、正直、モチベーションが削り取られるだけです。
しかし、別の方法で、エビングハウスの忘却曲線を前提とした勉強方法を取ることができます。
それは、一つの科目、一つの分野だけを、一定期間繰り返すことです。
例えば、連結会計だけを一定期間、インプットとアウトプットを繰り返します。
連結会計の論点を一つずつ、テキストや例題でインプットして、問題集や答練を解くというアウトプットを繰り返します。これで連結会計の全体を一周させます。
そしたら、もういちど、連結会計の全体を同じ方法でもう一周します。その際、定着している論点があれば、いきなりアウトプットだけをやってもいいと思います。
一定期間これを繰り返して、定着したな、と思えば、別の科目や分野に移ります。
移った後、しばらく連結会計は触らなくても大丈夫です。忘れてしまうことを心配するかもしれませんが、大丈夫です。
一定期間それだけを繰り返して、一回定着させておけば、多少放置していても、次に学習するときには圧倒的に効率よく思い出すことができます。
人の脳は、同じことを何度も繰り返して、自分の記憶に何度もアクセスしてやれば、脳みその回路がどんどん太く成長していきます。一度太くなった回路は、そう簡単には、もとには戻らなくなります。
ここでのポイントは、一定期間の繰り返しのなかで、確実に定着させることです。
覚える時には、何回も同じところに目を通して、何周もしていけば、自然と記憶していきます。
何度も歩いて通った道は、何も考えなくても、歩いていくことができるのと同じです。
記憶を定着させるために、何度も通りかかる、というイメージです。
ちなみに、私がこの方法を確立したきっかけとなった本はこちらです。時間があれば、読んでみてください。
また、何度も眺めていれば、「あのページの左端のボックス部分に書いてあったな」とか「あの論点は項目は3つあったな」とか、そんな風にイメージ的にも覚えることもできるようになってきます。
(ただし、私自身、イメージ記憶や瞬間記憶などという特殊能力的なものはありません。単に愚直に何回も何回も同じ場所を見ることで、自然と覚えていくだけの普通の作業です。)
記憶と理解については、こちらの記事でも言及していますので、ご参照ください。
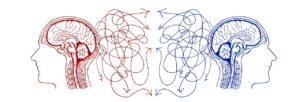
1種類の教材だけを使用する
テキストや参考書、レジュメやノートをインプットする方もいれば、答練や問題集の回答をひたすらインプットする方もいます。
私は1冊の予備校のテキストを繰り返し潰していくスタイルで、インプット用の教材は1種類と決めていました。別の種類の教材に手を広げるということはしませんでした。
インプット用の教材は、アウトプット(問題集や答練)の度に戻る場所です。
そのため、戻る場所がいくつもあると、非常に時間がかかるだけでなく、記憶が分散してしまうため、定着も遅くなり、非常に非効率です。
試験勉強は孤独と不安がつきもので、試験直前になればなるほど、この感覚は強まっていきます。
そこで、この1冊をさえ押さえれば大丈夫、という安心感が絶対に必要です。
予備校を選ぶポイントも、実はテキストが自分にしっくりくるかが重要でした。講師が補助レジュメを配るときは、どうしても必要なものだけをテキストの該当ページに挟み込むか書き写して集約していました。
いくつものテキストを同時並行で使用するのは、全くもってお勧めできません。ただでさえ分量が多いのに、学習量をさらに増やしてしまうからです。不安な気持ちから他のテキストに手を出してしまう気持ちは分かりますが、よほどのことがない限りは、目の前の予備校のテキストを信頼して、基本的なことを潰せば受かる試験です。
ただし、私も他予備校のテキストに興味を持って乗り換えた経験はあります。理由は、テキストが自分と相性が悪く使いずらい、あるいは、残念ながらテキストの質が低いから、でした。
そういう時は、思い切って、変えてみるのはアリです。
スキル②インプットとアウトプットを相互に繰り返す
知識をインプットをする。その知識をアウトプットする。そして、またインプットに戻る。結果的に飽きるほどの圧倒的なインプット量となる。
言い換えれば、テキストなどを読み込み知識を入れたら(インプット)、すぐに問題集や答練などでその知識を試すという事です。
とどのつまり、勉強とは、シンプルに、ひたすらこれを繰り返すだけの作業です。
繰り返せた数の分だけ勝利に近づきます。
たとえば、おすすめは決してしませんが、時々、短時間睡眠で鬼のようにやってる人が短期合格したなんて話がありますよね。(短時間の睡眠でも支障のないまれなタイプだと思います。)
これはインプットとアウトプットの回数が合格水準に達するのが早いからだと思います。
さらに、回数が短期間の間に積み重なるから、知識の蓄積が非常に効果的かつ効率的に行われたということだと思います。
「点を面にする」勉強スキル
アウトプットで練習をしたら、「都度」インプット用の教材に戻ることをお勧めします。
この方法は、本質的には「点を面にする」という作業になります。
答練や問題集の問題で出る知識が「点」、テキストの該当箇所の知識の集合が「面」。
具体的に説明します。
答練や問題集に出題された問題は、テキストの該当の箇所の一部分を切り取って、問題にしてるだけです。そして、そのテキストの該当箇所の知識は重要だよ、という問題作成者のサインとも言えます。
「点」だけをいくら押さえたって、本試験で全く同じ問題が出ない限りは解けないことになります。
だから、知識を「面」で押さえよう、ということです。
しかし、いきなり最初からテキストの知識を「面」ですべてを押さえるのは効率が悪いです。徐々に「点」を増やして濃い色にして「面」にしていくイメージです。
具体的には、テキストの関連する論点を、一度に網羅的に「面」で押さえるのではなく、まずは重要かつ出題頻度の高いところを問題集や答練などで「点」を押さえ、そこからテキストに戻ることを繰り返すことで、徐々に濃い色の「面」として押さえていく、ということです。
スキル③理解が難しい事も、分解すれば、一つ一つのパーツは理解可能な事である
内容によっては、一読しただけでは理解できないことがあります。
また、一度理解したつもりでも、実はよく分かっていなかった、ということもあります。
自分が分かるレベルのことに分解して、それを一つずつ積み重ねて理解していくのです。
すでに知っていることが、次の未知の事を理解するための「道具」になります。
そして、未知だったことを自分のものにすると、また一つ「道具」を手に入れます。
そうやって使える「道具」を、地道に、一つずつ増やしていくことで、いつの間にか、分からなかったことが分かるようになっていきます。
急がば回れ、千里の道も一歩から、です。
まとめ
最後に簡単にまとめます。
– 忘れることを前提にインプットする。
– 教材は1種類に絞って、何回も見ることで覚えてしまう。
スキル②: インプットとアウトプットを相互に繰り返す
– 「点」を「面」にする。
スキル③: 理解が難しい事も、分解すれば、一つ一つのパーツは理解可能な事である。
– 既知の「道具」を一つずつ増やしていく。
一言でいえば、一定期間、一つの分野で、インプットとアウトプットを繰り返す、ということですね。
以上、参考になれば幸いです。