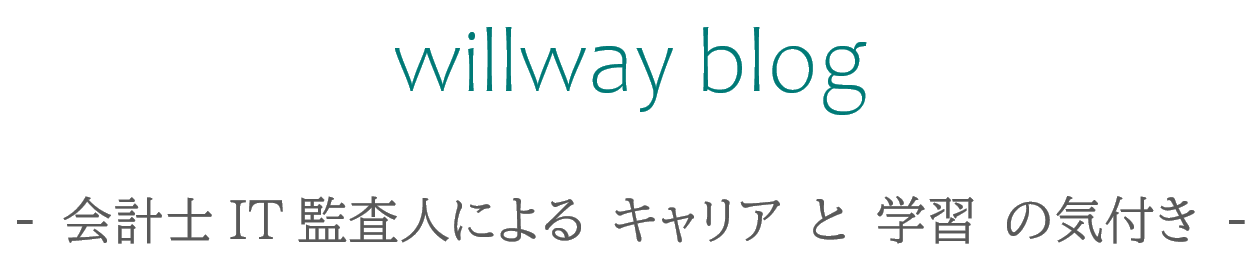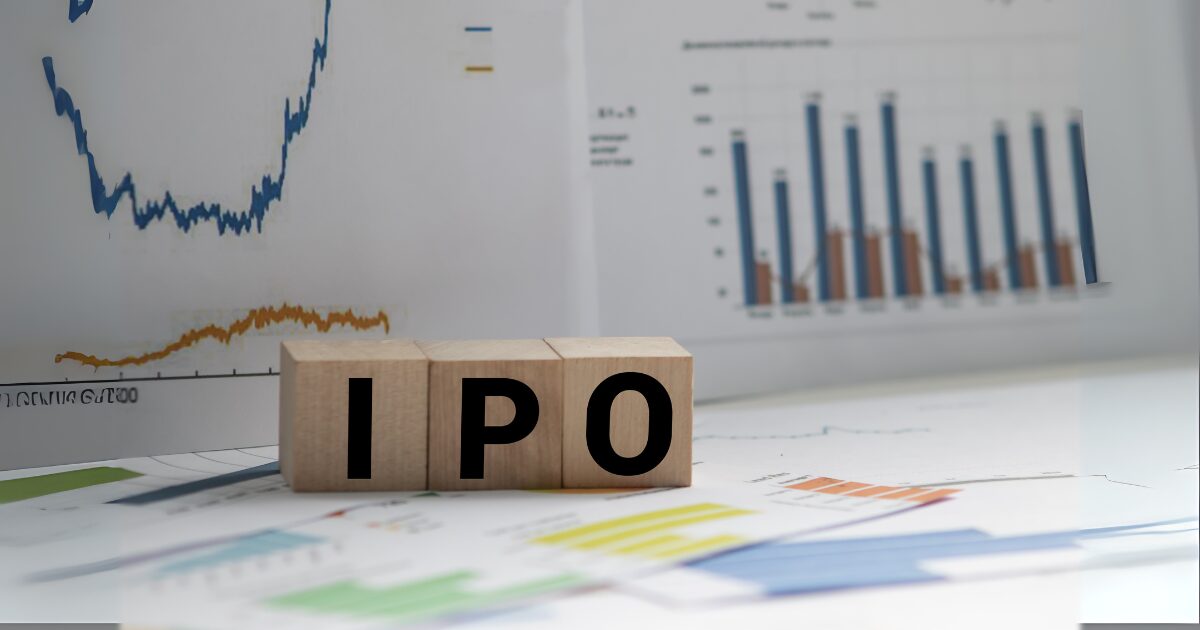今回はIT監査(システム監査)の領域で、法定監査と並んで、もう一つ内部統制の重要な業務をご紹介します。
既に監査法人やコンサルティング会社(監査法人のアドバイザリー)にて法定の監査業務を行っている場合には、
ご経験のある方も多いかもしれませんが、今回はIPO(株式上場)の支援業務です。
IT監査の経験が未経験の場合には、いきなりIPO支援から担当することは少ないという印象です。
この記事は、以下のような方に向けてIT統制監査の実務を紹介したいと思います。
- システムエンジニアとしてのキャリアを続けることに疑問を感じている人
- 監査法人でのIT監査経験をコンサルティングに活かしたい人
- IT監査職に興味がある人
- 公認情報システム監査人(CISA)やシステム監査技術者という資格を使って監査の仕事をしてみたい人
- 上場企業の内部監査で、IT統制の監査を受けているが、いまいちよく分からないという人
この記事を書く私の経歴は以下の通りで、情シス出身の現役のIT監査人です。
- 新卒で入った上場企業の情報システム部門で社内SEとして保守・運用に従事
- 監査法人(大手・中小)にて会計監査の一環としてのIT統制監査の外部監査に従事
- 会計系コンサルティングファームにてIT統制、ITリスクガバナンスの内部監査・経営者評価の支援アドバイザリーに従事
- 公認情報システム監査人(CISA)と公認会計士を保持
なお、IT監査の未経験者は、最初のキャリアとしては監査法人をオススメしているので、そのあたりは下記の記事をご参照ください。

では、まずは、IPO準備の概略から紹介します。
■ IPOの概要
□ IPOとは何か
IPO(Initial Public Offering)とは、新規株式公開または株式上場を指します。
つまり、それまで株式非公開であった企業が、証券取引所に株式を上場し、一般投資家でも株式の売買ができるようになることです。
IPOは、一般に、以下のようなメリットを目的に行われます。
1.資金調達力の向上
- 株式市場からの資金調達が可能になる
- 信用力が向上し、融資等の調達も容易になる
2.企業価値・知名度の向上
- 企業の社会的信用が高まる
- ブランド力の向上につながる
- 取引先との関係強化に繋がる
3.人材採用・定着
- 優秀な人材の採用が容易になる
- ストックオプション等の導入で従業員のモチベーション向上
4.経営管理体制の強化
- 内部統制の整備により経営の透明性が向上
- コーポレートガバナンスの強化
ただし、上場企業になることで、情報開示義務や内部統制の整備、コンプライアンスの強化など、さまざまな責任や義務も生じます。そのため、上場準備には通常2-3年程度の期間をかけて、体制を整備していく必要があります。
そこで、監査人の出番となります。
□ IPOのスケジュール
株式上場を証券取引所へ申請する期をN期と表現し、上場前の期間をN-3期、N-2期、N-1期と表します。
上場準備企業(IPO)の内部統制構築について、それぞれの期間でどのように進むのか、一般的な事例を用いて解説します。
□ N-3期(体制構築期間)
この時期は、内部統制構築の準備段階です。
- 内部統制の現状と改善事項の調査
- 各種規定の策定
- 稟議制度、予算管理制度等の導入
- 業務プロセスの構築、業務フローチャート、RCM(リスク・コントロール・マトリクス)等の整備
- 内部管理体制の整備(J-SOX対応※1)
- 上場準備のための人材確保(社内プロジェクトチームの結成など)
- 監査法人の選定
- 監査法人等によるIPO課題調査(ショートレビュー、予備調査※2)を受け、IPOのために検討すべき課題の洗い出し、優先順位をつけて順次改善
- IPO課題調査(ショートレビュー)で識別された課題は、監査法人等によるフォローアップを受ける
- 課題対応のため、監査法人等のアドバイザリー業務を利用することも可能
※1) J-SOX:「金融商品取引法」のうち主に内部統制に関する条文箇所を俗称で日本版SOX法(J-SOX)と呼びます。2002年にアメリカで制定されたサーベンス・オクスリー法(SOX法) を参考として制定されたため、日本版SOX法あるいはJ-SOXと呼ばれるようになりました。
※2) IPO課題調査(ショートレビュー、予備調査):監査法人等が上場に向けて、社内管理体制や財務報告に関する体制に対して、あるべき姿にするため、課題抽出を行うことです。
□ N-2期(直前々期・整備/運用期間)
上場会社と同様の管理体制の整備、運用の段階に入っていることが望まれます。
- 予備調査の結果を踏まえ、改善事項の対応や、内部管理体制の整備を進める
- 主幹事証券会社を選定し、上場申請書類の作成を開始
- 課題対応のため、引き続き監査法人等のアドバイザリー業務を利用することも可能
□ N-1期(直前期・試運転期間)
この時期は、主幹事証券会社に上場申請書類を提出します。
上場会社と同様の管理体制を期首から運用することが求められます。
- 主幹事証券会社による上場申請書類の審査
- 上場会社と同様の管理体制の期首からの運用
- 監査契約(準金商法監査)を締結し、N-1期に係る監査を受ける。
- 課題対応のため、引き続き監査法人等のアドバイザリー業務を利用することも可能
□ N期(申請期・本格運用期間)
N期は、いよいよ上場申請を行う期であり、内部統制の本格運用期間です。
- 上場申請書類の完成および証券取引所への上場申請
- 監査契約を締結し、N期に係る監査を受ける
- 課題対応のため、引き続き監査法人等のアドバイザリー業務を利用することも可能
□ 上場後
上場後も継続的な内部統制の維持・改善が必要です。
- 内部監査による定期的な制度の理解・定着度合いの確認
- 内部監査による新たな課題の発見・対応支援
- 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の制度(J-SOX)への対応
□ 内部統制報告書の開示
上場企業は、上場後最初に到来する事業年度末から内部統制報告書を開示する必要があります。ただし、以下の通り免除の場合もあります。
1.開示のタイミング
上場後最初の決算期から3ヶ月以内に内部統制報告書を提出しなければなりません。
2.監査証明の免除
新規上場企業は、一定規模の企業を除き、上場後3年間は内部統制報告書に係る監査証明が免除されます。
ただし、監査証明が免除されても、内部統制報告書の作成と提出自体は義務となります。
(一定規模とは:上場日の属する事業年度の直前事業年度に係る連結貸借対照表もしくは貸借対照表に資本金として計上した額が100億円以上、又は当該連結貸借対照表もしくは貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が1,000億円以上の会社は適用除外)
■ IPO準備企業への支援業務
IPOについて一通り紹介したところで、IT監査人がどのような役割を果たすかを補足致します。
ほとんどが上述の流れの中で登場する内容となります。
- 監査法人またはアドバイザリー所属のIT監査人は、ITに関する内部統制のIPO課題調査(ショートレビュー、予備調査)を実施します。
- 会社から委託を受け、ITに関する内部統制の構築のサポート業務を実施します。
(内部管理体制や承認プロセスの構築の支援、文書作成の支援) - 会社から委託を受け、ITに関する内部統制の整備・運用の評価を実施します。
なお、基本的には、財務報告に関連するIT・システムを評価するため、公認会計士等の会計監査を担当するチームと共同でIT監査をしていくことになります。
■ まとめ
いきなりIT監査人としてIPO支援から入る人は少ないと思います。
監査法人やアドバイザリーにて、IT監査を経験している方が、IPO支援の業務に部分的にアサインされて経験されるケースが多いでしょう。
ただ、こうした業務もあるということを参考にして頂ければと思います。
監査法人の業務や転職に興味ある方は、以下をご参照ください。