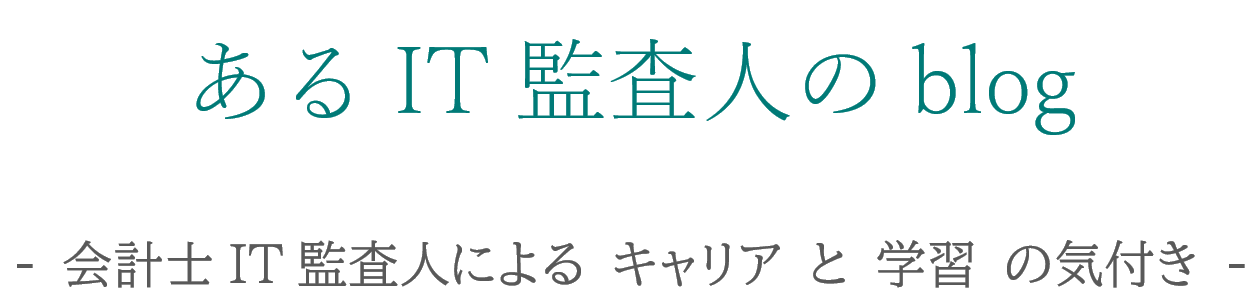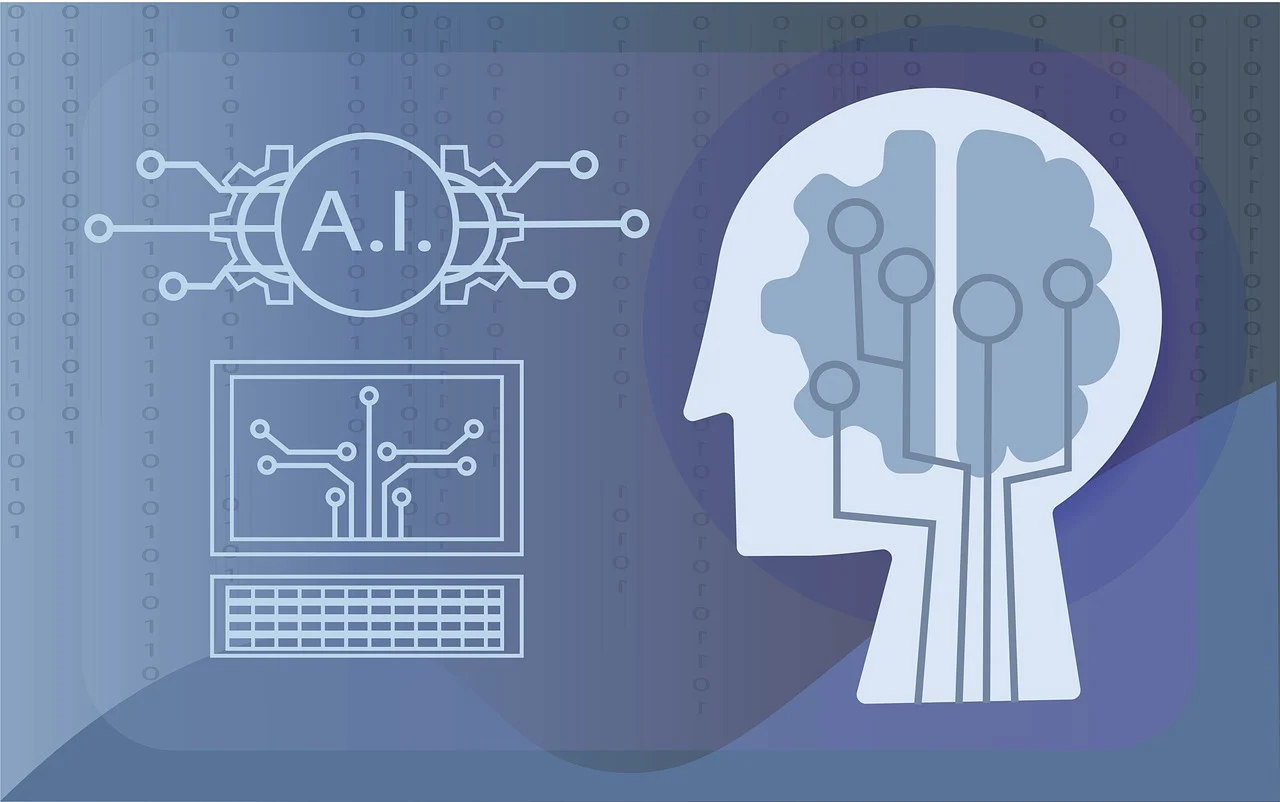AIの進化により、税理士や公認会計士は職を奪われるという研究結果が、よく引用されてきました。
2013年のオックスフォード大学の研究発表で、結構前ですが、最近のトピックであるChatGPTというAIの驚異的な進化を目の当たりにして、いよいよ現実的に秒読みになってきたと考えています。
いわゆる会計専門家と言われる職業についている私の立場から考察してみたいと思います。
そして、我々会計士のような特定の専門家にとって、AI時代において、今後のキャリアをどのように立ち回るのかについて、重要な視点を書いてみたいと思います。
ChatGPTとは
現時点で、ChatGPTについて多くを説明する必要はないかと思います。
既にお使いになった方も多いと思いますが、衝撃の能力ですよね。
生成系AI(Generative AI)と呼ばれるもので、まったく新しいものをクリエイティブかつ現実的に生み出すAIで、
ChatGPTのようにテキストを生み出すものだけでなく、画像、動画、音声など様々なものを生成する能力を持つ人工知能(AI)がありますよね。
まさに2022年はこの生成系AIの進化が飛躍的となった年になり、テキストの生成系AIとしては、ChatGPTが一般公開早々に1億を超えるユーザーを誇ることになりました。
これはある種のトレンドではなく、時代の重要な転換点を迎えているという評価がもはや一般的となっています。
そして、あらゆる人がこの時代に直面して、自分自身の立ち回り方や、子育て、教育にも全く新しい視点を入れていくべきだと考えています。
そのような観点から、今回、記事を書いています。
AI時代にヒトの専門家に残る業務
私は常々、会計士として監査や会計アドバイザリーの職務にあたる中で、毎年のようにアップデートされる会計、監査や税務の法令や基準をキャッチアップしてきて、思っていたことがありました。
業務をこなすためには、一人の人間として、これほどのキャッチアップを続けていかなければならないことに、危機感を感じていました。
なぜならば、まさに言われてきたように、膨大な基準や法令のデータベースをAIが取り込み、論理的に問題解決するロジックを持っていれば、我々の作業のほとんどは必要なくなるからです。
基準や法令を知っていて、それを問題に対して適用するということへの権威性が、ヒトの専門家からAIに取って代わられるのは時間の問題と考えています。
したがって、将来的にヒトに残るものとしては以下のようものが考えられます。
・クライアントとの生身のコミュニケーション(ただし技術的な対話はAIに譲っていくことになる)
・AIの出す解の検討(言い換えると、ヒトとAIとの対話・ブレインストーミング)
・AIとヒトとの共同作業結果に対する責任の所在
・チームのマネジメント
これには多くの賛否がありますが、劇的な業務量の減少がこれにより進むでしょう。
ヒトに残る優位性とは
よく、人間特有の生身のコミュニケーションは、AIに奪われないだろう、と言われますが、個人的にはこの立場にすら懐疑的です。
生身のコミュニケーションで形作られてきたビジネスの現場で育った人間にとっては、郷愁として、そのような願望を頂くかもしれません。
しかしながら、AIネイティブの時代に生まれ育った人間にまで、その感覚は芽生えるでしょうか。
この資本主義と能力主義の時代において、ヒトによる生身のコミュニケーションの必要性と、AIによる知識や問題解決能力の優位性・権威性は、どちらが優先されるでしょうか。
おそらく、AIネイティブの時代には、後者が多数派になるのではないかと思うのです。
前者がなくなることは、もちろんないと思います。
ヒトとしての生身の温度感のあるコミュニケーションは、どんな場面にでも必要とされ続けるでしょう。
しかし、こと専門家の絡む業務やビジネスの現場においては、優先度が逆転するのではないかと思うのです。
したがって、こうしたビジネスの現場では、ヒトの優位性は大きく希薄化していくことになるでしょう。
ヒトの専門家の生存戦略
さて、自分自身のためにも、専門家の生き残る道はどのようなものか考えたいと思います。
たとえば以下のようなものを挙げてみました。
・分野横断的な専門性のリンキング
・ヒトやチーム、クライアントを含めた総合的なマネジメント(調整)能力
■AIとのブレインストーミング能力(専門性に裏打ちされたAIへの質問力)
ヒトが専門性を持ち続ける意義は、この点に残ると思います。
今後、AIは業務における所与となるので、AIを使いこなすという視点が求め得られるようになります。
AIとの共同作業で、成果を出していくことが求められる以上、いかにAIの性能を引き出すかということに力点が置かれると思います。
そこでは、ヒトが勉強や実務経験で得た専門性を元に、的確にAIに質問してやり、AIの解を検討する必要があります。
■分野横断的な専門性のリンキング
業務によっては様々な専門家の集積した経験や知識でサービス提供する場合があります。
例えば、業界の慣行、会計、法律、税務、ITと横断的に知見が求められる場合がありますが、
それらをうまく連携させて成果を出していくことが求められます。
それらをうまくリンクさせていく必要があるとき、そのマネジメント能力が求められると思うのです。
ただし、それすらも多かれ少なかれ、AIは学習していくことにはなるはずですので、ここも最終的にはAIとの協働にはなってくるでしょう。
■ヒトやチーム、クライアントを含めた総合的なマネジメント(調整)能力
最終的には、この手のマネジメントは、最もヒトに残りやすい業務と考えます。
なぜなら、このマネジメントはとても曖昧なものであるし、明確な答えのないものだからです。
全体としてうまく機能するような微妙な調整は、やはりヒトに残ると考えます。
ただ、いずれにしても、専門家のような知的ホワイトカラーはよほど飛びぬけた何かを持っていない限りは、生き残りが難しくなるのは間違いないでしょう。
まとめ
別の記事↓で紹介した『働き方 2.0 vs 4.0』(橘玲 著)の最後に、AIが世界に浸透した後の世界を紹介されています。

やがて機械がすべての仕事を行うユートピアあるいはディストピアが来るとしていて、シリコンバレーの起業家であるジェリー・カプランの表現が引用されています。
そこでは、AIのような「合成頭脳」が人間との協働の期間を経て、やがて人間が合成頭脳に「飼われている」世界が来ると予言しています。
身の毛もよだつような話ですね…
以上、ざっと検討してみましたが、今後も私自身の思考の変化や整理を、継続して発信していければと思います。